 こちら12月6日の第2デラウェア園。いよいよ剪定作業をはじめました。
こちら12月6日の第2デラウェア園。いよいよ剪定作業をはじめました。
さて、松本市の「新規就農者育成対策事業第4期」に採用されてはや4年が経ちました。去年の秋に3年間のこの事業上での研修期間を終えて、今年が一人前の農業者としてのスタートでした。
農業をはじめてみてはじめてわかったこと、というのがいろいろありますが、なかでも、この事業のなかのある制度の存在が本当にありがたかった、と実感しています。
それは必要な農機具を貸与してくれることでした。わたしの場合、経験も知識もなにもないIターン就農で、当然のことながらさしあたってどんな農機具が必要なのかということも全く知りませんでした。それを中古品でも一通り揃えたら100万円以上する機器類をほぼ無償で借りることができたことが、なによりもありがたかったです。
今、全国あちこちの自治体で新規就農者の誘致事業をやっていますが、必要な農機具をほぼ無償で貸してくれるという制度はわたしの知る限り松本市だけだと思います。この点を松本市はもっとアピールしてもいいと思います(笑)。
今年もこの事業に4名の方が採用されたようなんですが、先日そのうちの一人の方からお電話がありました。新規就農するに際してのさしあたっての相談だったのですが、その内容がまさに4年前に私が抱え込んでいた問題と同じだったのでとても他人事とは思えず、ずいぶん電話で話し込んでしまいました。
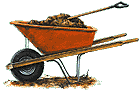
この地でぶどうを作り始めて5年目を迎えようとしています。気分はもう新規就農者ではありません。ぶどうでいかにして生計を立てていくかということの他に、地域のために自分はいったい何ができるのか、地域の中で自分はどういう存在であるべきか、ということを考えるようになりました。
今、産地が抱えている大きな問題のひとつに、生産者の高齢化があります。
後継者があるところはよいのですが、そうばかりではありません。「10年後この産地ははいったいどうなっちゃってるんだ?!」という会話があちこちで聞かれます。
しかしながら都会に目を転じれば、わたしのようなIターンにしろUターンにしろ、また思い度や本気度に温度差こそあっても、農業をやりたいと思っている人は何万人っているはず。地域のために自分がなにができるのか、を考える時、ここにひとつのヒントがありそうだなと思っています。
後継者不足に悩む地域と都会の潜在的新規就農希望者予備軍のパイプ役になれないかな。地域の実情と、新規就農希望者誰もが抱える悩みや課題、その両方を知っているからこそ、です。
これからはいろいろなところで自分なりに情報発信をしていきたいと思っています。そしてその結果として、1年にひとりでも2年にひとりでもいい、やる気のある新規就農者が長い目で見て何人もこの地に根づいてくれればいいな、と思っています。

「農業の専門性を修得し、経営者としての資質向上、国際感覚等を養い、先進的で模範的な農業経営を実践する地域農業のリーダー育成をはかる」という、行政が運営中心の勉強会があります。「松本新興塾」といって、今年の5月からわたしも参加して勉強させてもらっています。
食糧自給率や輸入農産物、地産地消や食育問題など、世界の中の日本という位置づけで日本の食と農の現状を知り、その知識を地域活動に生かすことが究極の目的です。地域のために自分に何ができるか。この勉強会からもいろんなヒントを得たいと思っています。
もうひとつは「黄華」です。山辺産のデラウェアは日本でも一、二の高単価を誇るブランド品です。そして次なるブランド品を創出するべく地域一体となって取り組んでいるのが「種無し」「大粒」「皮ごと」と三拍子揃った黄白色の純粋欧州種のぶどう、「黄華」なのです。
初めて食べた時、その食味はちょっとした衝撃でした。世の中にこんなうまいぶどうがあったんかいというように。今、20アールのピオーネ園を全面この「黄華」に改植中です。本格的な収穫ができるようになるにはまだ3〜4年以上かかりますが、近い将来、地域の中で「主要な黄華生産者」のひとりに数えられるように、地域に「なくてはならない生産者」のひとりになりたいと思っています。
 |
| その「黄華」ですが、防寒対策としてワラを厚く巻きました。一般的にぶどうは寒さに強いといわれていますが、それでも冬の間はマイナス10度以下になる日が何度かあります。また「黄華」は純粋欧州種で、やや凍害に弱いということで、しっかりと主幹を保温してあげました。 |
11月の農事録でも書きましたが、デラウェアにしても巨峰にしても、今年は栽培面ではずいぶんと手ごたえを感じました。もちろん技術的にはまだまだで、技術向上の余地がいくらもあるのですが、ただここがこうできればもっと良くなるというポイントがいくつもわかって、その辺の感度が結構つかめた感じです。そのあたりを来年は上手にやっていきたいと思っています。
来年も楽しみ楽しみ...。
 |
| これはデラウェアの若木。発泡ポリエチレンの防寒帯を巻きました。毎年使いまわしても清潔なままなのでけっこう愛用しています。 |
はぁ〜...。
このブログの原稿書きもようやくこれで終わりかな...。プレッシャーから開放されるうれしい気持ちがある反面、いざ終わりとなると、ちょっと寂しい気もします。ここまでお読みいただいた方、本当にありがとうございました。これにて「中川さんちの農事録」は終了します。
でもブログは終了しても「なかがわ葡萄園」はまだはじまったばかり。安全でおいしい葡萄を消費者の皆様にお届けするべくこれからもがんばっていきます。どうかみなさん、応援してください。
最後に、わたしのホームページを紹介させていただきます。そのものずばりの「なかがわ葡萄園」といいます。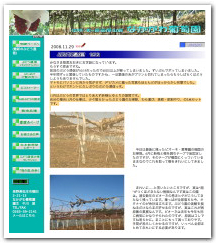 わたしのホームページで、もともとは3年前から自分の脱サラ奮闘記録みたいなものを、私と妻の親兄弟親戚友人知人会社の元同僚上司先輩後輩とそれこそ内輪の人たちに対して「ぶどう通信」というホームページ風メールを送っていました。それがだんだん面白くなってしまってこの5月にとうとうホームページを作ってしまったという次第。
わたしのホームページで、もともとは3年前から自分の脱サラ奮闘記録みたいなものを、私と妻の親兄弟親戚友人知人会社の元同僚上司先輩後輩とそれこそ内輪の人たちに対して「ぶどう通信」というホームページ風メールを送っていました。それがだんだん面白くなってしまってこの5月にとうとうホームページを作ってしまったという次第。
この「いいJAん!信州」みたいな立派なものではありませんが、ぶどう作りと一緒で1から100まで全部自分の手作りです。だから自分なりに結構愛着を持って運営しています。これからはホームページでお会いしましょう。
みなさんこれまで1年間ありがとうございました。
 なかがわ葡萄園のホームページ
なかがわ葡萄園のホームページ
